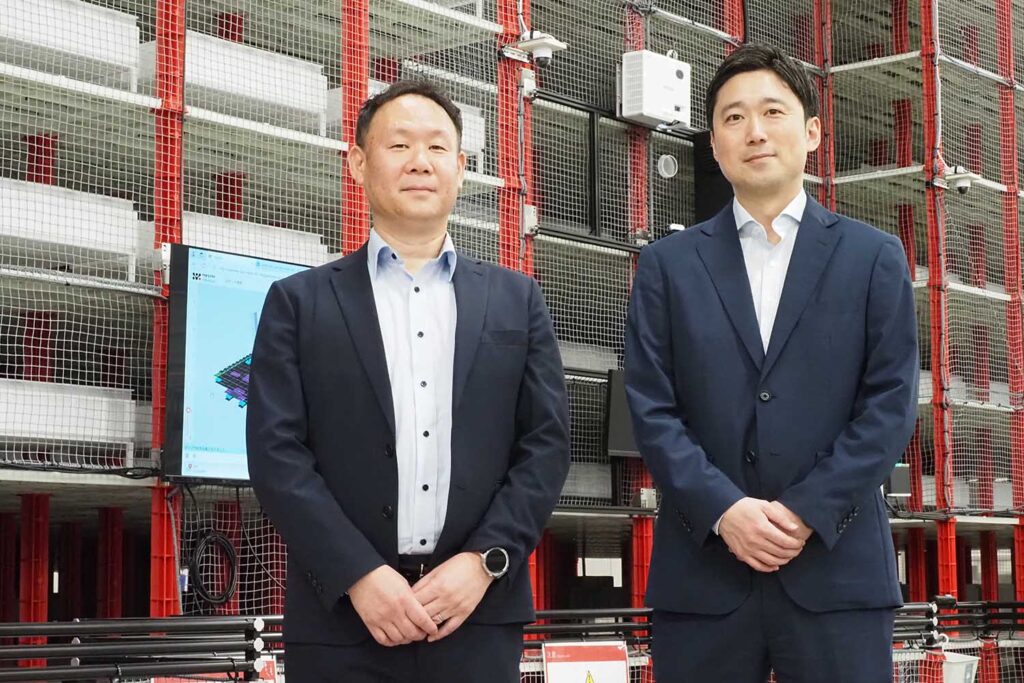人員不足対策とオペレーション標準化を主目的に自動化を推進
株式会社アルプス物流は、大手3PLのロジスティード株式会社を親会社に持つ3PL企業で、国内外で保管・運送・輸出入といった物流を単独で担うグローバル総合物流企業です。同社は今回、千葉県成田市の大栄倉庫にラピュタロボティクスの自在型自動倉庫「ラピュタASRS」を導入され、2025年5月に稼働開始を迎えています。そこで本記事では、倉庫自動化を検討あるいは推進される皆さまの参考となるよう、アルプス物流様にラピュタASRSの導入背景や稼働開始に至るまでの道程を伺いました。
株式会社アルプス物流 大栄倉庫
・所在地:千葉県成田市
・事業内容:総合物流業
・導入区分:新規倉庫
・ASRS稼働日:2025年5月
・取扱品目:電子部品
・ASRS設置面積:約360㎡
・現場天井高:5.5~6m
・階層数:9階層
・ロボット台数:16台
・エレベータ数:4基
・保管用ビン数:4,000
・ピッキングST数:2台
・目標生産性:非公開
今回、ラピュタロボティクスのラピュタASRSを導入いただいたアルプス物流が倉庫自動化に着手したそもそもの背景には、もはや社会的な課題となっている人員不足の問題がありました。働き手が不足するという事象が現場に及ぼす影響は、それぞれの現場によって異なります。アルプス物流が抱えていた課題感を、同社保管BU 部長の野殿征範氏は次のように説明します。
「人の採用が難しい時代に入り、それが5年後、10年後と年を経るごとに厳しくなる現場の苦しい現実を見てきています。当社の場合、他業種、例えばEC販売業の企業様と大きく異なるのは、まず取り扱っているものが精密部品であるという点です。温度・湿度管理、静電気・防塵対策、振動対応など様々な面で取扱いに注意しなければいけませんし、何万とあるSKU(在庫管理の最小識別単位)すべてにバーコードやJANコードがあるわけではない中での作業になります。そのため、当社の現場作業は一般的な倉庫内作業と比較すると複雑な箇所もあり、教育にも時間がかかります。スポットで採用した人員では手に負えない業務もあるため長期で勤めてくれる人が必要なのですが、長期で良い人材に来てもらうということが、ここ数年でどんどん難しくなってきたな、というのを感じていました。」
こうした背景をふまえ、この人員不足を現場レベルの課題と切り捨てるのではなく、アルプス物流という企業として真剣に受け止め、向き合ってきたからこそ同社は自動化に舵を切ることになりました。結果、ピースピッキングに対応するバケット型の自動倉庫を、2020年に兵庫県西宮市の拠点で初めて導入し、その後2024年には横浜と名古屋の現場で立て続けに稼働を開始。そして今回2025年5月に千葉県成田市の大栄倉庫で自在型自動倉庫「ラピュタASRS」がその稼働を開始しています。
なぜ他社製品導入経験がある中でラピュタASRSを選定したか

野殿氏によれば、今回ラピュタASRSを導入した大栄倉庫は、成田空港に程近い千葉県芝山町に位置する成田営業所の外部倉庫として2024年5月に開所。成田営業所の機能は、輸出を控える電子部品のストック&デリバリーです。大栄倉庫の開所までは、成田空港近くに2箇所の外部倉庫を構えていましたが、今回の大栄倉庫はその外部倉庫2箇所を1つに集約して機能させるという役割も持っています。
「2箇所の外部倉庫も既に満床で、これ以上物量を増やせない状態でした。そこでこの大栄倉庫に2拠点分の業務を集約することで、効率化と業務拡大を図る狙いがありました。(野殿氏)」
この大栄倉庫は、成田営業所へ車で約30分とアクセスが良い上に成田空港にも近く、全館空調を完備している点から電子部品の保管にも向いています。また、エレベータによる上げ下げが発生しない平屋倉庫で天井高が5.5~6mと成田営業所と比較して高く、自動倉庫による自動化にも向いていました。
では、いざ自動倉庫の導入となった際に、なぜアルプス物流はラピュタASRSを選んだのでしょうか?
「従来の自動倉庫選定では、なるべく現場の1日の処理(オーダー)件数が多いことで選んでいましたが、これまで他社の自動倉庫を導入・運用してきた経験から、入出庫の能力、つまり作業の処理能力とスペース効率を両方兼ね備えたものであるというのが一番重要でした。この条件を満たすものが最も効果を発揮できる自動倉庫ということになりますので、この部分の比較を最も慎重に行いました。スペースはそこまで効率化できないがスピードは非常に速い、逆にスピードは遅いがスペース効率は非常に良いといろいろな自動倉庫がある中で、処理能力とスペース効率のバランスが最も良かったのがラピュタASRSでした。我々の保管物量と入出庫能力にぴったり合うという点で、ラピュタさんが最有力候補に上がったということです。(野殿氏)」
見逃してはいけないWMS連携の柔軟性
ラピュタASRS導入を決めたその他の要因を尋ねたところ、野殿氏からはソフトウェア、つまりアルプス物流のシステムの中核を担うWMSであるACCS (Apls Cargo Center System) との連携に対する、ラピュタASRSのソフトウェア面での柔軟性のお話が挙げられました。
「我々も自社のWMSを持っているので、システムをいくらかカスタムして我々のWMSとつなげ、運用が上手くいくようにしたいという希望がずっとありました。システムに対する考え方は非常に重要なウェイトを占めます。その点について他社さんより柔軟性があったというのも決め手だったと思います。(野殿氏)」

自動倉庫を通して提供されるマテハンメーカー側のシステムやソフトウェアに対し、ユーザー側では既に自社で使用しているWMSが運用されているケースが多く存在します。特にアルプス物流のように自社オリジナルのWMSを含めたシステムが顧客(荷主企業)へのサービスにおいても重要な位置を占めているようなケースでは、「主」の立場で運用されるのはあくまでユーザー側のWMSでなければならず、またその重要機能を損なうことなく円滑に連携を行いたい、というのがユーザー側のニーズとなります。ラピュタロボティクスでは、ラピュタASRSに標準でWMSが付帯しているものの、ユーザー側で使用されているWMSなどの管理システムと柔軟にAPIを用いて連携を行うことで、このユーザー側のニーズを満たせるよう努めています。
「我々は自社のWMSを何十年にもわたって使っており、効率向上を目指してシステムの細やかな改善を随時重ねてきました。そのため自社のWMSをベースに自動倉庫を動かしたいという方向でずっと考えています。このため、どうしても自動倉庫側のWMSを使ってくださいと言われると、我々の答えはノーとなります。アルプス物流のWMSと自動倉庫を組み合わせる際、自社のデータだけで自動倉庫を使いたいという希望が我々にはあるのですが、自動倉庫メーカーさんの方でもシステムを標準化したいという思いがあるので、全くカスタムに対応してくれないところもありますし、少しなら対応できますよ、というところもあるのですが、それだと二重で操作する等の煩雑さや余計な工数が増えてしまいます。トータルの効率として考えると、我々のWMSだけでやれる状態が最も効果が出るので、我々のWMSを活かしてもらえるような自動倉庫側のシステムでなければいけないかな、と思っています。(野殿氏)」
また、同社経営企画部 経営企画課 課長の渡邊真広氏は更に具体的な例を交えて解説してくださいました。
「WMSは、例えば商品が届いたら入庫の処理をして保管し、お客様から出荷指示が来たら、倉庫内の複数のロケーションに保管されているので、それを引き当てし、ピッキング、梱包、出荷…という流れで処理を行うことになります。アルプス物流のACCSは自分たちで作ったものであり、使い慣れたシステムで、既に人もシステムも効率良く運用しています。自動倉庫側のシステムが柔軟であれば我々が演算した結果だけを自動倉庫側のシステムに渡す、といった形で運用できます。アルプス物流側のWMSは我々が自分たち用にカスタマイズした効率が良いものを使い、自動倉庫側のシステムもその自動倉庫が最も効率良く動くものを使う、という状態が実現できるようなカスタムができる方が、我々にとっては都合がいいということになります。(渡邊氏)」
また野殿氏によれば、自動倉庫との連携を目的にカスタムを行った自社のWMSは、今後他の拠点に自動倉庫を導入するとなった際にも横展開の形でそのまま使用できるという点も大きなメリットになるということです。アルプス物流では、自社のWMSであるACCSを全社全拠点で、グローバルで使用しており、例えば国内拠点で勤務していた社員が海外拠点に異動することがあっても、そのまま同じシステムを使用して業務に当たることができる体制を構築し、最初から高い効率でシステムを運用できる状態を実現しています。これは人事異動に限らず、国内海外を問わず新たな拠点を開設した際にも、一般的には稼働効率を一定水準まで引き上げるのにある程度の期間が必要ですが、アルプス物流では立ち上げ当初から高効率で現場を稼働させることができる体制が整っている、とも言い換えられるでしょう。
「グローバル展開している物流会社において国内でWMSを統一しているケースはあるのですが、グローバルレベルで統一できている企業はなかなか無いのではないかと思います。かつ自社開発のシステムで、という点では尚更でしょう。」と渡邊氏はグローバル3PL市場におけるアルプス物流の強みを解説します。
賃借物件への導入に有利な免震/制震のアンカーレス設計
野殿氏によれば、スペース効率と処理能力に次いで導入の決め手になったのがラピュタASRSの「自在型」たる所以にあたる部分でした。ラピュタASRSの「自在型自動倉庫」とは、免震/制震構造のブロックを自由に組み上げることで導入時に自由自在にレイアウトできるだけでなく、導入後にもレイアウト変更や他拠点への移設にも対応できること、ピッキング後の出荷準備工程への連携(仕分け、荷合わせ、順立て等も自動倉庫内で自動化できる)などオペレーション面でも高い自由度が発揮できることを指しています(詳細解説記事はこちら)。今回アルプス物流では、その中でも免震/制震構造に由来するアンカーレスの部分も導入決定の一因となっています。
「保管効率と処理能力の両方を兼ね備えているなというのを感じたのと、あとはアンカーを打たずに免震/制震構造になっているというところが一番大きなポイントでした。名古屋と横浜は自社物件の倉庫なのですが、自社の建物だと天井が高い建物がほぼなく、3.5mの天井高が標準になっています。名古屋の場合は昨年(2024年)新築し、自動倉庫を入れる前提の設計で5.5mの天井高にしているのですが、それ以外の既存の自社物件だと5.5mの高さはありません。そのため、今後自動倉庫を入れていくとなると賃借倉庫になる。アンカーも打たなければいけないとなると、なかなか導入ハードルが高くなるなというのがありました。また、仮に今後また別の倉庫に移転や集約を行うとなった場合でも、ラピュタASRSであれば移設にも対応できる。その点も決定要因の一つになっています。(野殿氏)」

野殿氏が指摘した通り、こと自動倉庫において物流倉庫としての収益に直結する処理能力(出荷能力)を高くすれば取り回しを行うスペースが犠牲となるため保管効率が低下し、逆に高密度保管を行うほど取り回しを行う空間が減るため処理能力が落ちる ── こうしたトレードオフの関係が成立してしまいがちな処理能力と保管効率を高水準で両立させることがラピュタASRSの開発コンセプトであり、また倉庫物件の平面図に反映されるレベルの固定設備となる自動倉庫を、「どこにでも設置できる」「どこへでも持っていける」という据え置き型の非固定設備として、尚且つ免震/制震構造による安全性を担保した上で開発したことで、より幅広い現場への導入、そしてより多くの倉庫を自動化によって「人にやさしい現場」にすることをラピュタロボティクスは目指しています。そして、アルプス物流でもまた、自動化と人員の関係性について取り入れている考え方がありました。
自動化で得られるのは人の「活人化」
自動化を推進するということは、自動化が導入された現場の、そのプロセスにおける必要人員数を低減できるということで、自動化設備においては一般的に言われる「省人化」という効果から定量的なROI(投資対効果)が算出されることも多くあります。しかしこの点で、自動化を推進するアルプス物流では物流業界ではまだ珍しい「活人化」というコンセプトを取り入れています。同社のコンセプトを渡邊氏が解説してくださいました。
「活人化というコンセプトを取り入れているのは、我々はどんどん省力化を進めて1つの仕事に対する必要人員数を減らそうとはしているのですが、減らした分の人たちをそのまま労務費用(コスト)として削減するのではなく、別の現場や別の業務に回ってもらうということを推進しているためです。人を活かすということで活人と表現しています。今までの仕事が自動化で無くなったからといって雇い止めをするわけではないというのが我々の基本的なスタンスです。(渡邊氏)」

以下の白いボタンからは、自在型自動倉庫「ラピュタASRS」が30分でわかる主要機能解説ウェビナー動画をご確認いただけます。実際の製品デモや導入に向けたご質問やご相談は、その更に下の赤いボタンよりお問合せください。